News and Announcements [in Japanese]
地磁気センターニュース

★ 一覧 ★

地磁気世界資料解析センター News No.122 2010年7月30日
1.新着地磁気データ
前回ニュース(2010年5月25日発行, No.121)以降入手、または、当センターで入力したデータのうち、
オンラインデータ以外の主なものは以下のとおりです。
オンライン利用データの詳細は (http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/catmap/index-j.html) を、観測所名の
省略記号等については、観測所カタログ (http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/catmap/obs-j.html) をご参照ください。
また、先週の新着オンライン利用可データは、(http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/wdc/onnew/onnew-j.html)で
御覧になれ、ほぼ2ヶ月前までさかのぼることもできます。
Newly Arrived Data(off-line)
(1)Annual Reports and etc.
NGK (Apr. - Jun., 2010)、KIR (Jul.,2004 - 2005)、Indian 6 obs. (2006)
(2)Kp index: (http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/kp/index-j.html)
May - Jun., 2010
2.AE指数とASY/SYM指数
1996-1999年のProvisional AE指数の算出と、2000-2007年のProvisional AE指数の再計算を行いました。
http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/ae_provisional/index.html
これで、AE指数は懸案であった長年のギャップを埋められました。
また、2010年6月分までの1分値ASY/SYM指数を算出し、ホームページに載せました
(http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/aeasy/index-j.html)。
2010年4月分までのProvisional AE指数も上記アドレスからダウンロード可能です。
3.電磁気でみる地殻内流体の不均質分布とその地震発生場との関連
1.はじめに
地殻を構成する岩石の比抵抗は、主として岩石の空隙や鉱物の粒界に存在する流体の存在とそのつながり
によって決定される。そのため、地殻の比抵抗構造を推定することによって、微量に存在する地殻内流体を
高感度に捉えることができる。本稿では、自然電磁場を用いる電磁探査法(MT法)によって見えてきた“内陸
地震地域の流体分布”について、ここ数年の成果を概観する。
2.内陸地震地域の地震発生層と比抵抗構造のレビュー
内陸地震地域では、地震発生層は地殻の高比抵抗部に存在し、その下方に非常に顕著な低比抵抗異常が存在
しているということがわかった。この特徴は、東北脊梁(北由利断層・千屋断層・北上山地西縁断層)
(Ogawa et al., 2001; 小川,2002a)、1963年宮城県北部地震地域(Mitsuhata et al., 2001)、長町利府
断層 (小川ほか,2005)、糸魚川静岡構造線北部(Ogawa et al., 2002; 小川, 2002b; Ogawa & Honkura,
2004)、2007年能登半島地震震源域(Yoshimura et al., 2008)、2008年岩手宮城内陸地震(Mishina,
2009)で共通して見出されてきている。
糸魚川静岡構造線北部地域では、地殻中深部の低比抵抗異常の分布する地域が、GPSによる面積ひずみの
大きい地域とよく対応することも見出された(Ogawa and Honkura, 2004)。長町利府断層では、地表の水
平変位の分布を存在するための断層深部延長が、脊梁直下の下部地殻にある低比抵抗異常に対応することが
明らかにされた(小川ほか, 2005)。
これらのことから、低比抵抗異常体には流体が存在し、そこでは塑性変形が可能になる一方で、その周辺
の高比抵抗部では塑性変形ができずに地震発生にいたるという図式が考えられる。あるいは、低比抵抗側に
存在する流体が高比抵抗側(流体に乏しい領域)に間歇的に侵入することによって高比抵抗側(地震発生
層)の間隙圧を高めて、地震が発生するという仮説も成り立つ(たとえばOgawa et al., 2001; Sibson,
2009)。
一方で、これらの流体がどのように供給されるかを知ることは重要である。紀伊半島では、低比抵抗層へ
の流体の供給がフィリピン海プレートから来ていることが比抵抗構造からも明らかにされた(Umeda et al.,
2006a)。MT法探査からは、紀伊半島中南部の深度20-40kmの範囲に低比抵抗異常が検出された。その底面は
沈み込むフィリッピン海プレート上面に相当し、非火山性の長周期微動が観測されている深度に対応する。
また低比抵抗層の上方には地殻内地震が発生しており、これは前述の内陸地震発生場の特徴に合致している。
低周波数微動発生源でプレートから水が供給され、それが上方の高比抵抗部(深度25km以浅)に侵入すること
によって地殻内の地震が発生していることを示唆する。
また、火山前線上の鳴子火山周辺地域や、非火山であるが高温である飯豊山地(Umeda et al., 2006b)
においては、中深部地殻低比抵抗体が存在し、それが高温域の直下に向かって浅くなる背斜構造が得られた。
さらにそれを地震発生と比較すると、地震の下限はこれら中深部地殻低比抵抗体上面に一致する。すなわち、
地震は低比抵抗体を避けるようにその上方の高比抵抗体に発生していることがさらに精密化された。これも、
上述の内陸地震地域における比抵抗構造の特徴と同じである。
海外の長大な横ずれ断層であるトルコ国北アナトリア断層(Tank et al., 2003, 2005)、ニュージーランド国
アルパイン断層(Wannamaker et al., 2009)、インドネシア国スマトラ断層に関しては、現在、研究プロジェク
トが進行中である。このうち、ニュージーランド国アルパイン断層について次節で紹介する。
3.最近の成果―ニュージーランドアルパイン断層の探査
ニュージーランド南島では、長さ500kmにわたる右横ずれ断層であるアルパイン断層が北東-南西方向に島を
縦断している(図1)。
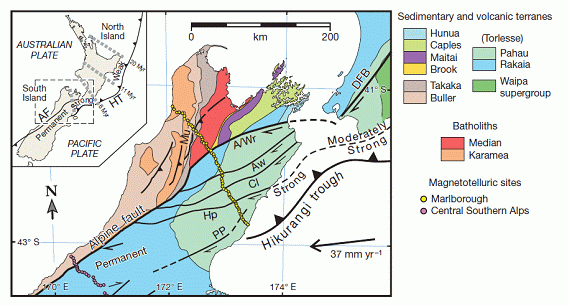 <図1:ニュージーランド南島北部を横断するMT測線。>
南島北部のマルボロ地域では、アルパイン断層に並行する5つの横ずれ断層が存在しているが、その地域の
地質が単純であり、それらが南東側に向けて順に若くなるので、断層の成熟度と断層の地下構造との関係を
研究するのに都合がよい場となっている。Wannamakerほか(2009)では、マルボロ地域200kmを横断するMT
探査を実施し、比抵抗モデルを示した(図2)。
<図1:ニュージーランド南島北部を横断するMT測線。>
南島北部のマルボロ地域では、アルパイン断層に並行する5つの横ずれ断層が存在しているが、その地域の
地質が単純であり、それらが南東側に向けて順に若くなるので、断層の成熟度と断層の地下構造との関係を
研究するのに都合がよい場となっている。Wannamakerほか(2009)では、マルボロ地域200kmを横断するMT
探査を実施し、比抵抗モデルを示した(図2)。
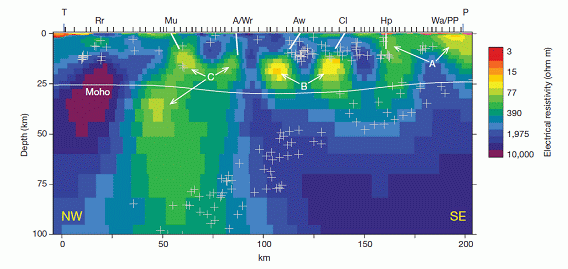 <図2:ニュージーランド南島北部を横断するMT測線の2次元断面解析。
白い十字が震源位置を表す。Mu,A/Wr,Aw,Cl,Hp, Wa/PPはそれぞれ断層の
位置を表す。図中のA,B,Cにおける流体の役割については図3に示す。>
重要な特徴は、断層の成熟度によって異なっている。南東側の若い断層では、まだ未固結な堆積層の中で
破砕することによって、低比抵抗体内部で地震が発生している(図2および図3A)。
<図2:ニュージーランド南島北部を横断するMT測線の2次元断面解析。
白い十字が震源位置を表す。Mu,A/Wr,Aw,Cl,Hp, Wa/PPはそれぞれ断層の
位置を表す。図中のA,B,Cにおける流体の役割については図3に示す。>
重要な特徴は、断層の成熟度によって異なっている。南東側の若い断層では、まだ未固結な堆積層の中で
破砕することによって、低比抵抗体内部で地震が発生している(図2および図3A)。
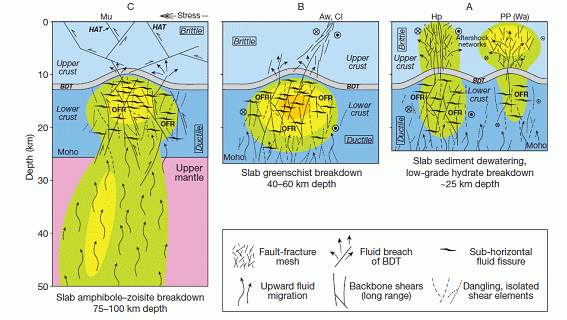 <図3:流体の分布形態と地震発生の関連。
右からA,B,Cの図は、それぞれ図2中に対応する。>
ついで、成熟した各横ずれ断層では、脆性塑性境界の下方に低比抵抗異常がそれぞれ分布している。ここで
は、トラップされている被圧流体が、地震とともに上方に運ばれ、地震を誘発するというモデルで説明する
ことができる(図2および図3B)。流体を含み変形が容易な下部地殻があり、その上方の地殻で地震が起き
ていると考えることもできる。アルパイン断層のさらに北側のMurchisonでは、20世紀初頭にM7を超える逆断
層型の内陸地震が発生しているが、そこには深度100kmにおけるプレートから脱水反応で発生し、上昇する流体
の柱(鉛直状の低比抵抗)がある(図2)。豊富な流体が存在することによって、空隙圧が高まり、通常では
起こり得ない高角の逆断層運動を可能にしたと考えられる(図3C)。この特徴は東北日本でも見出されて
いるものと共通する。
4.まとめと展望
ここ数年間の研究から、地震発生場における比抵抗構造研究から以下のことを明らかにすることができた。
(1)内陸地震地域の中深部地殻(mid-crust)の比抵抗構造はきわめて不均質で、地殻中深部の流体の分布が
不均質であることが示唆される。(2)低比抵抗異常の上面が地震発生層の下面に対応することが多くの場合に
見出されるが、成熟度の低い断層では低比抵抗層内部で地震が発生している。(3)多くの場合、巨大内陸地震
の本震が低/高比抵抗境界の高比抵抗側で発生している。(4)地殻中深部の低比抵抗異常体がひずみ集中に対応
している。以上の事柄は、最近発生した内陸地震で普遍的に見ることができる。特に高角な逆断層で内陸地震
が発生するためには、地殻深部から十分な流体の供給があることが示唆される。
今後、電磁気観測点の面的な配置や、3次元比抵抗構造インバージョンによって3次元的な地殻内流体の分布
が詳細に解き明かされつつある。実際に、平成21年度から開始された科学研究費補助金・新学術領域研究“地殻
流体:その実態と沈み込み変動への役割”においては、東北地方で上部マントルから地殻上部に至る3次元比
抵抗構造の解析に向けて、電磁気観測が進められているところである。
(http://www.geofluids.titech.ac.jp/index.html)
引用文献:
Mishina, M., 2009., Distribution of crustal fluids in Northeast Japan as inferred from resistivity surveys, Gondwana Research, 16, 3-4, 563-571.
Mitsuhata, Y., Y. Ogawa Y., M. Mishina, T. Kono, T. Yokokura and T. Uchida, 2001, Electro magnetic heterogeneity of the seismogenic region of
1962 M6.5 Northern Miyagi Earthquake, northeastern Japan, Geophys. Res. Lett., 28, 4371-4374.
Ogawa Y. and Y. Honkura, 2004. Mid-crustal electrical conductors and their correlations to seismicity and deformation at Itoigawa-Shizuoka
TectonicLine, Central Japan, Earth Planets Space, 56, 1285-1291
Ogawa Y., M. Mishina, T. Goto, H. Satoh, N. Oshiman, T. Kasaya, Y. Takahashi, T. Nisitani, S. Sakanaka, M. Uyeshima, Y. Takahashi, Y. Honkura,
and M. Matsushima, 2001, Magnetotelluric imaging of fluids in intraplate earthquakes zones, NE Japan back arc, Geophys. Res. Lett., 28, 3741-
3744.
Ogawa, Y., S. Takakura, and Y. Honkura, 2002, Resistivity structure across Itoigawa-Shizuoka tectonic line and its implications for concentrated
deformation, Earth Planets Space, 54, 1115-1120.
小川康雄、2002a. 電磁波で地殻構造と水の動きを見る、出羽丘陵から脊梁山地の地殻比抵抗断面、科学、204-208.
小川康雄、2002b. 広帯域MT法による内陸地震地域のイメージング、地震学会ニュースレター、vol.14、no.2、16-18.
小川康雄・三品正明・本蔵義守、2005. 長町利府断層の深部比抵抗構造-地殻変形と地震発生との関連,月刊地球, 号外地球 No.50, 71-74.
Sibson, R.H., Rupturing in overpressured crust during compressional inversion-the case from NE Honshu, Japan, 2009. Tectonopysics, 473, 3-4,
404-416.
Tank, S. B., Y. Honkura, Y. Ogawa, N. Oshiman, M. K.Tuncer, C. Celik, E. Tolak, and A. M. Isikara, 2003, Resistivity structure in the western
part of the fault rupture zone associated with the 1999 Izmit earthquake and its seismogenic implication, Earth Planets Space, 55, 437-442.
Tank, S.B., Y. Honkura, Y. Ogawa, M. Matsushima, N. Oshiman, M. K. Tuncer, C. Celik, E. Tolak, and A. M. Isikara, 2005. Magnetotelluric imaging
of the fault rupture area of the 1999 Izmit (Turkey) earthquake, Phys. Earth Planet. Inter., 150, 213-225.
Umeda, K., K. Asamori, T. Negi and Y. Ogawa, 2006, Magnetotelluric imaging of crustal magma storage beneath Mesozoic crystalline mountains in a
non-volcanic region, Northeast Japan, Geochem. Geophys. Geosyst., 7, Q08005 doi: 10.1029/2006001247.
Umeda, K., Y. Ogawa, K. Asamori, and T. Oikawa, , 2006. Aqueous fluids derived from a subducting slab: observed high 3He emanation and conductive
anomaly in a non-volcanic region, Kii Peninsula southwest Japan, J. Volcanol. Geotherm. Res., 149, 47-61.
Umeda, K., K. Asamori, T. Negi and Y. Ogawa, Magnetotelluric imaging of crustal magma storage beneath Mesozoic crystalline mountains in a non-
volcanic region, Northeast Japan, 2006. Geochem. Geophys. Geosyst., 7, Q08005 doi: 10.1029/2006001247.
Uyeshima, M., Y. Ogawa, Y. Honkura, S. Koyama, N. Ujihara, T. Mogi, Y. Yamaya, M.. Harada, S. Yamaguchi, I.Shiozaki, T. Noguchi, Y. Kuwaba,
Y. Tanaka, Y. Mochido, N. Manabe, M. Nishihara, M. Saka and M. Serizawa, 2005, Resistivity imaging across the source region of the 2004 Mid-
Niigata Prefecture earthquake (M6.8), central Japan, Earth Planets Space, 57, 441-446
Yoshimura, R., N. Oshiman, M. Uyeshima, Y. Ogawa, M. Mishina, H. Toh, S. Sakanaka, H. Ichihara, I. Shiozaki, T. Ogawa, T. Miura, S. Koyama,
Y. Fujita, K. Nishimura, Y.Takagi, M. Imai, R. Honda, S. Yabe, S. Nagaoka, M. Tada, and T. Mogi, 2008. Magnetotelluric observations around
the focal region of the 2007 Noto Hanto Earthquake (Mj6.9), Central Japan, Earth Planets Space, 60, 117-122.
Wannamaker, P.E., T.G. Caldwell, G. R. Jiracek, V. Maris, G.J. Hill, Y. Ogawa, H. M. Bibby, S. B. Bennie, and W. Heise, 2009. The fluid and
deformation regime of an advancing subduction system; Marlborough, New Zealand, Nature, 460, 733-U90, doi:10.1038/nature08204.
(小川康雄 - 東京工業大学・火山流体研究センター)
4.「伊能忠敬の『山島方位記』から19世紀初頭の日本の地磁気偏角を解析し、活用する。その7」
(1) 研究対象の「山島方位記」が国宝指定のニュースを耳にして思うこと。 (辻本元博)
本研究は、伊能忠敬の全国測量時の磁針測量方位角台帳「山島方位記」六十七巻(伊能忠敬記念館蔵) に
記載の推定約20万件程度の測量方位角データから、地磁気偏角を解析する研究です。1917年東京帝大の大谷
亮吉氏(後に京都帝大理学部教授)が「山島方位記」に記載の江戸深川黒江町の伊能忠敬隠宅の偏角解析値が
大著「伊能忠敬」岩波書店に記述されたことは日本の地磁気の永年変化の把握に大変に重要なことです。
但し、「考究は頗る有益にして・・・然れども(伊能の測量の再現は・・)容易の業にあらざるのみならず
・・・詳細なる研究は他日に譲り」として中断された研究とは知らずに、1999年に研究を開始、偶然京都大学
地磁気世界資料解析センターを訊ね、地磁気センターニュース2005.1.24№89号から毎年地磁気偏角の解析
結果を投稿しています。昔は非常に困難であった解析も、パソコン等の発達で可能になりつつあり、今後の
時代の要請に応え得るデータを解析しようとしております。昨年末からは、数学とコンピューター専門
の面谷明俊氏も加わり、スピード化と精度向上中です。解析地点数は100の台を超えました。報道ではこの度、
伊能忠敬の史料を国宝指定にする答申が出され、「山島方位記」も重文から国宝になるとのことです。
「山島方位記」が国宝指定になりますと、日本列島という広範囲に亘り、解析作業で地磁気偏角と同時に、
日本各地の歴史地理の内容も同時にわかる、世界でも珍しい精緻な測量台帳の国宝になります。「山島方位
記」の解析と解析結果の活用は、北東アジア全域に関連する伊能測量当時の地磁気偏角の解析は勿論、伊能
図にも記載の無い歴史地誌との両面で、相当規模の遺跡の発掘に匹敵する重要なことと考えます。
(2) 新たに判明した各地の地磁気偏角
①島根半島の地磁気偏角と傾向 (面谷明俊)
島根半島東部の松江付近及び弓濱半島では1°W前後を示すが、西部の出雲平野では1°20′Wから1°30′W
の範囲へと西偏を増す傾向が認められた。
表1.本州の1806年島根半島の地磁気偏角 (解析・現地確認 面谷明俊)
<図3:流体の分布形態と地震発生の関連。
右からA,B,Cの図は、それぞれ図2中に対応する。>
ついで、成熟した各横ずれ断層では、脆性塑性境界の下方に低比抵抗異常がそれぞれ分布している。ここで
は、トラップされている被圧流体が、地震とともに上方に運ばれ、地震を誘発するというモデルで説明する
ことができる(図2および図3B)。流体を含み変形が容易な下部地殻があり、その上方の地殻で地震が起き
ていると考えることもできる。アルパイン断層のさらに北側のMurchisonでは、20世紀初頭にM7を超える逆断
層型の内陸地震が発生しているが、そこには深度100kmにおけるプレートから脱水反応で発生し、上昇する流体
の柱(鉛直状の低比抵抗)がある(図2)。豊富な流体が存在することによって、空隙圧が高まり、通常では
起こり得ない高角の逆断層運動を可能にしたと考えられる(図3C)。この特徴は東北日本でも見出されて
いるものと共通する。
4.まとめと展望
ここ数年間の研究から、地震発生場における比抵抗構造研究から以下のことを明らかにすることができた。
(1)内陸地震地域の中深部地殻(mid-crust)の比抵抗構造はきわめて不均質で、地殻中深部の流体の分布が
不均質であることが示唆される。(2)低比抵抗異常の上面が地震発生層の下面に対応することが多くの場合に
見出されるが、成熟度の低い断層では低比抵抗層内部で地震が発生している。(3)多くの場合、巨大内陸地震
の本震が低/高比抵抗境界の高比抵抗側で発生している。(4)地殻中深部の低比抵抗異常体がひずみ集中に対応
している。以上の事柄は、最近発生した内陸地震で普遍的に見ることができる。特に高角な逆断層で内陸地震
が発生するためには、地殻深部から十分な流体の供給があることが示唆される。
今後、電磁気観測点の面的な配置や、3次元比抵抗構造インバージョンによって3次元的な地殻内流体の分布
が詳細に解き明かされつつある。実際に、平成21年度から開始された科学研究費補助金・新学術領域研究“地殻
流体:その実態と沈み込み変動への役割”においては、東北地方で上部マントルから地殻上部に至る3次元比
抵抗構造の解析に向けて、電磁気観測が進められているところである。
(http://www.geofluids.titech.ac.jp/index.html)
引用文献:
Mishina, M., 2009., Distribution of crustal fluids in Northeast Japan as inferred from resistivity surveys, Gondwana Research, 16, 3-4, 563-571.
Mitsuhata, Y., Y. Ogawa Y., M. Mishina, T. Kono, T. Yokokura and T. Uchida, 2001, Electro magnetic heterogeneity of the seismogenic region of
1962 M6.5 Northern Miyagi Earthquake, northeastern Japan, Geophys. Res. Lett., 28, 4371-4374.
Ogawa Y. and Y. Honkura, 2004. Mid-crustal electrical conductors and their correlations to seismicity and deformation at Itoigawa-Shizuoka
TectonicLine, Central Japan, Earth Planets Space, 56, 1285-1291
Ogawa Y., M. Mishina, T. Goto, H. Satoh, N. Oshiman, T. Kasaya, Y. Takahashi, T. Nisitani, S. Sakanaka, M. Uyeshima, Y. Takahashi, Y. Honkura,
and M. Matsushima, 2001, Magnetotelluric imaging of fluids in intraplate earthquakes zones, NE Japan back arc, Geophys. Res. Lett., 28, 3741-
3744.
Ogawa, Y., S. Takakura, and Y. Honkura, 2002, Resistivity structure across Itoigawa-Shizuoka tectonic line and its implications for concentrated
deformation, Earth Planets Space, 54, 1115-1120.
小川康雄、2002a. 電磁波で地殻構造と水の動きを見る、出羽丘陵から脊梁山地の地殻比抵抗断面、科学、204-208.
小川康雄、2002b. 広帯域MT法による内陸地震地域のイメージング、地震学会ニュースレター、vol.14、no.2、16-18.
小川康雄・三品正明・本蔵義守、2005. 長町利府断層の深部比抵抗構造-地殻変形と地震発生との関連,月刊地球, 号外地球 No.50, 71-74.
Sibson, R.H., Rupturing in overpressured crust during compressional inversion-the case from NE Honshu, Japan, 2009. Tectonopysics, 473, 3-4,
404-416.
Tank, S. B., Y. Honkura, Y. Ogawa, N. Oshiman, M. K.Tuncer, C. Celik, E. Tolak, and A. M. Isikara, 2003, Resistivity structure in the western
part of the fault rupture zone associated with the 1999 Izmit earthquake and its seismogenic implication, Earth Planets Space, 55, 437-442.
Tank, S.B., Y. Honkura, Y. Ogawa, M. Matsushima, N. Oshiman, M. K. Tuncer, C. Celik, E. Tolak, and A. M. Isikara, 2005. Magnetotelluric imaging
of the fault rupture area of the 1999 Izmit (Turkey) earthquake, Phys. Earth Planet. Inter., 150, 213-225.
Umeda, K., K. Asamori, T. Negi and Y. Ogawa, 2006, Magnetotelluric imaging of crustal magma storage beneath Mesozoic crystalline mountains in a
non-volcanic region, Northeast Japan, Geochem. Geophys. Geosyst., 7, Q08005 doi: 10.1029/2006001247.
Umeda, K., Y. Ogawa, K. Asamori, and T. Oikawa, , 2006. Aqueous fluids derived from a subducting slab: observed high 3He emanation and conductive
anomaly in a non-volcanic region, Kii Peninsula southwest Japan, J. Volcanol. Geotherm. Res., 149, 47-61.
Umeda, K., K. Asamori, T. Negi and Y. Ogawa, Magnetotelluric imaging of crustal magma storage beneath Mesozoic crystalline mountains in a non-
volcanic region, Northeast Japan, 2006. Geochem. Geophys. Geosyst., 7, Q08005 doi: 10.1029/2006001247.
Uyeshima, M., Y. Ogawa, Y. Honkura, S. Koyama, N. Ujihara, T. Mogi, Y. Yamaya, M.. Harada, S. Yamaguchi, I.Shiozaki, T. Noguchi, Y. Kuwaba,
Y. Tanaka, Y. Mochido, N. Manabe, M. Nishihara, M. Saka and M. Serizawa, 2005, Resistivity imaging across the source region of the 2004 Mid-
Niigata Prefecture earthquake (M6.8), central Japan, Earth Planets Space, 57, 441-446
Yoshimura, R., N. Oshiman, M. Uyeshima, Y. Ogawa, M. Mishina, H. Toh, S. Sakanaka, H. Ichihara, I. Shiozaki, T. Ogawa, T. Miura, S. Koyama,
Y. Fujita, K. Nishimura, Y.Takagi, M. Imai, R. Honda, S. Yabe, S. Nagaoka, M. Tada, and T. Mogi, 2008. Magnetotelluric observations around
the focal region of the 2007 Noto Hanto Earthquake (Mj6.9), Central Japan, Earth Planets Space, 60, 117-122.
Wannamaker, P.E., T.G. Caldwell, G. R. Jiracek, V. Maris, G.J. Hill, Y. Ogawa, H. M. Bibby, S. B. Bennie, and W. Heise, 2009. The fluid and
deformation regime of an advancing subduction system; Marlborough, New Zealand, Nature, 460, 733-U90, doi:10.1038/nature08204.
(小川康雄 - 東京工業大学・火山流体研究センター)
4.「伊能忠敬の『山島方位記』から19世紀初頭の日本の地磁気偏角を解析し、活用する。その7」
(1) 研究対象の「山島方位記」が国宝指定のニュースを耳にして思うこと。 (辻本元博)
本研究は、伊能忠敬の全国測量時の磁針測量方位角台帳「山島方位記」六十七巻(伊能忠敬記念館蔵) に
記載の推定約20万件程度の測量方位角データから、地磁気偏角を解析する研究です。1917年東京帝大の大谷
亮吉氏(後に京都帝大理学部教授)が「山島方位記」に記載の江戸深川黒江町の伊能忠敬隠宅の偏角解析値が
大著「伊能忠敬」岩波書店に記述されたことは日本の地磁気の永年変化の把握に大変に重要なことです。
但し、「考究は頗る有益にして・・・然れども(伊能の測量の再現は・・)容易の業にあらざるのみならず
・・・詳細なる研究は他日に譲り」として中断された研究とは知らずに、1999年に研究を開始、偶然京都大学
地磁気世界資料解析センターを訊ね、地磁気センターニュース2005.1.24№89号から毎年地磁気偏角の解析
結果を投稿しています。昔は非常に困難であった解析も、パソコン等の発達で可能になりつつあり、今後の
時代の要請に応え得るデータを解析しようとしております。昨年末からは、数学とコンピューター専門
の面谷明俊氏も加わり、スピード化と精度向上中です。解析地点数は100の台を超えました。報道ではこの度、
伊能忠敬の史料を国宝指定にする答申が出され、「山島方位記」も重文から国宝になるとのことです。
「山島方位記」が国宝指定になりますと、日本列島という広範囲に亘り、解析作業で地磁気偏角と同時に、
日本各地の歴史地理の内容も同時にわかる、世界でも珍しい精緻な測量台帳の国宝になります。「山島方位
記」の解析と解析結果の活用は、北東アジア全域に関連する伊能測量当時の地磁気偏角の解析は勿論、伊能
図にも記載の無い歴史地誌との両面で、相当規模の遺跡の発掘に匹敵する重要なことと考えます。
(2) 新たに判明した各地の地磁気偏角
①島根半島の地磁気偏角と傾向 (面谷明俊)
島根半島東部の松江付近及び弓濱半島では1°W前後を示すが、西部の出雲平野では1°20′Wから1°30′W
の範囲へと西偏を増す傾向が認められた。
表1.本州の1806年島根半島の地磁気偏角 (解析・現地確認 面谷明俊)
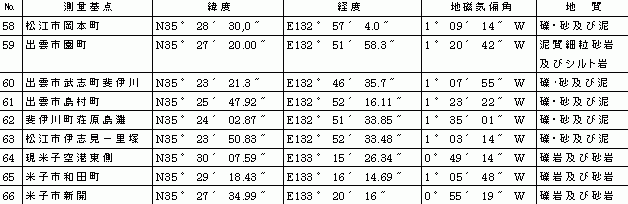 図1. 島根半島での偏角解析済み測量基点
図1. 島根半島での偏角解析済み測量基点
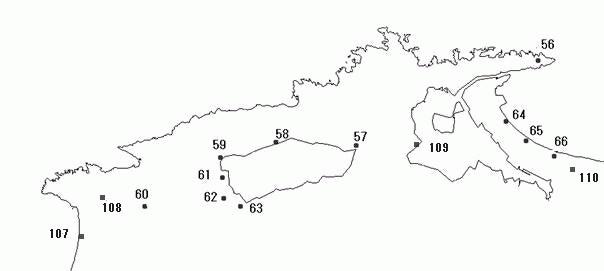 56 美保関日和山(センターニュース107号参照)57松江末次京屋灘座敷(センターニュース109号参照)
107 出雲市湖陵町108出雲市大社町109 松江市大海崎110米子市上福原(センターニュース119号参照)
②淡路島と高知県西部
表2. 淡路島の地磁気偏角1808年 (解析・現地確認:辻本元博)
56 美保関日和山(センターニュース107号参照)57松江末次京屋灘座敷(センターニュース109号参照)
107 出雲市湖陵町108出雲市大社町109 松江市大海崎110米子市上福原(センターニュース119号参照)
②淡路島と高知県西部
表2. 淡路島の地磁気偏角1808年 (解析・現地確認:辻本元博)
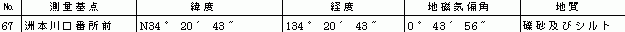 表3. 高知県西部の地磁気偏角1808年 (解析: 辻本元博・面谷明俊 現地確認:辻本元博)
表3. 高知県西部の地磁気偏角1808年 (解析: 辻本元博・面谷明俊 現地確認:辻本元博)
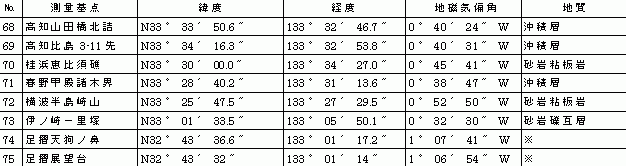 68は参勤交代北山街道の、高知城下出入り口の山田番所の山田橋北詰、69は北山街道と他の街道との追分
(分岐)比嶋の旧交差点(詳細に復元)、70は桂浜の恵比寿礁(海上保安庁信号所のすぐ西)、71は甲殿と諸木の
村境海岸、72の崎山113.9mは頂上への道無く試算にとどめる。測量対象地点には、石鎚山南峯は「前○森」
と瀬戸内側からの登山道の「前社森」と同様の表現かと思われる山名表現であり、土佐側での石鎚山信仰を
物語る。73は地元伝承の「一里塚」の地点の海岸と確認した。(後述)。
足摺は総て伊佐浦と表現され、三つの岬が東西に並んでいる。74の伊佐浦三印は足摺の天狗の鼻、二印
は足摺の展望台(地元ではテンポウダイと呼ぶ)、いずれも伊佐浦一印(足摺岬)の東側の岬 ※花崗岩閃長岩
及び斑レイ岩。
山島方位記二十二 五月七日イ印 (高知桂浜恵比須礁ハエでの測量) (解析面谷明俊 撮影辻本元博)
68は参勤交代北山街道の、高知城下出入り口の山田番所の山田橋北詰、69は北山街道と他の街道との追分
(分岐)比嶋の旧交差点(詳細に復元)、70は桂浜の恵比寿礁(海上保安庁信号所のすぐ西)、71は甲殿と諸木の
村境海岸、72の崎山113.9mは頂上への道無く試算にとどめる。測量対象地点には、石鎚山南峯は「前○森」
と瀬戸内側からの登山道の「前社森」と同様の表現かと思われる山名表現であり、土佐側での石鎚山信仰を
物語る。73は地元伝承の「一里塚」の地点の海岸と確認した。(後述)。
足摺は総て伊佐浦と表現され、三つの岬が東西に並んでいる。74の伊佐浦三印は足摺の天狗の鼻、二印
は足摺の展望台(地元ではテンポウダイと呼ぶ)、いずれも伊佐浦一印(足摺岬)の東側の岬 ※花崗岩閃長岩
及び斑レイ岩。
山島方位記二十二 五月七日イ印 (高知桂浜恵比須礁ハエでの測量) (解析面谷明俊 撮影辻本元博)
 <図2:山島方位記二十二 五月七日イ印桂浜恵比須礁 (はえ) になる伊能忠敬記念館蔵>
<図2:山島方位記二十二 五月七日イ印桂浜恵比須礁 (はえ) になる伊能忠敬記念館蔵>

 <写真1:高知桂浜駐車場北側海上保安庁 <写真2:山島方位記二十三の伊佐浦二印
信号所のすぐ西の堰堤上がイ印の位置。> (足摺岬園地展望台)から東側の伊佐浦。
三印(天狗の鼻)を望む手前反対側の後方
が伊佐浦一印(足摺岬) 解析:辻本元博>
表4. 愛媛県西部瀬戸内の地磁気偏角 (解析: 面谷明俊 現地確認未了)
<写真1:高知桂浜駐車場北側海上保安庁 <写真2:山島方位記二十三の伊佐浦二印
信号所のすぐ西の堰堤上がイ印の位置。> (足摺岬園地展望台)から東側の伊佐浦。
三印(天狗の鼻)を望む手前反対側の後方
が伊佐浦一印(足摺岬) 解析:辻本元博>
表4. 愛媛県西部瀬戸内の地磁気偏角 (解析: 面谷明俊 現地確認未了)
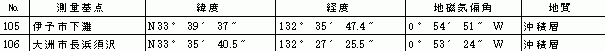 ③今後の課題: 中国四国と九州での1度西偏の分布地域の相互関係の解明が、依然として課題といえる。
1806年の島根半島東部から、瀬戸内沿岸の福山阿武兎観音堂、1808年の四国足摺での1°W台、1810年
1812年の九州南部大隈半島や種子島の1°W台との関係の解明を要す。
④壱岐北端の小島の偏角
表5. 壱岐北端の小島の1813年の地磁気偏角 (解析: 辻本元博 現地確認未了)
③今後の課題: 中国四国と九州での1度西偏の分布地域の相互関係の解明が、依然として課題といえる。
1806年の島根半島東部から、瀬戸内沿岸の福山阿武兎観音堂、1808年の四国足摺での1°W台、1810年
1812年の九州南部大隈半島や種子島の1°W台との関係の解明を要す。
④壱岐北端の小島の偏角
表5. 壱岐北端の小島の1813年の地磁気偏角 (解析: 辻本元博 現地確認未了)
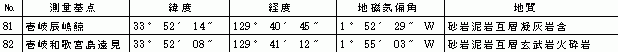 (注) 佐賀平野の1°40′Wから対馬北西部2°30′Wへの途中の壱岐は、火山で磁針が定まりにくいが、
壱岐最北端の離れ島の辰島と若宮島では1°50′W台になり、既に報告済みの対馬北西部No.76~80の
5地点の平均値は2°30′Wであるが、解析難渋中の対馬南部の2°W台以上の可能性が見えてきた。
「鯨」、「遠見」は、捕鯨組織の鯨見と船舶の藩の遠見番所の各詳細位置判明。但し、遠隔地の離島
からの小島の為に現地には行けておりません。
図3. 西日本での解析済み測量基点(Kenmap)
(注) 佐賀平野の1°40′Wから対馬北西部2°30′Wへの途中の壱岐は、火山で磁針が定まりにくいが、
壱岐最北端の離れ島の辰島と若宮島では1°50′W台になり、既に報告済みの対馬北西部No.76~80の
5地点の平均値は2°30′Wであるが、解析難渋中の対馬南部の2°W台以上の可能性が見えてきた。
「鯨」、「遠見」は、捕鯨組織の鯨見と船舶の藩の遠見番所の各詳細位置判明。但し、遠隔地の離島
からの小島の為に現地には行けておりません。
図3. 西日本での解析済み測量基点(Kenmap)
 (3) 著名西洋科学者の長崎での観測データと佐賀、天草で整合し、年変化も小さい。 (辻本元博)
長崎に近い佐賀県小城市牛津、西砥川、天草下島富岡曲淵での1°40′前後の解析値は、表6のKrusenstern
の長崎での地磁気偏角観測結果とも符合するだけでなく、19世紀前半の長崎では年変化は約1分~1分30秒
の西偏増程度であり、伊能測量の1806~1813年の期間の、異なる年の中国四国九州地方測量での永年変化
の差も、約10分以内のレベル程度かと予想される。
表6.
(3) 著名西洋科学者の長崎での観測データと佐賀、天草で整合し、年変化も小さい。 (辻本元博)
長崎に近い佐賀県小城市牛津、西砥川、天草下島富岡曲淵での1°40′前後の解析値は、表6のKrusenstern
の長崎での地磁気偏角観測結果とも符合するだけでなく、19世紀前半の長崎では年変化は約1分~1分30秒
の西偏増程度であり、伊能測量の1806~1813年の期間の、異なる年の中国四国九州地方測量での永年変化
の差も、約10分以内のレベル程度かと予想される。
表6.
 但し、「山島方位記」からの長崎での偏角の解析は、残念ながら測量基点から測量対象地点の山々への距離
が短かいために、解析は困難を伴い解析未了であるが、今後方法の改善を試みたい。
(4) 山島方位記から測量基点の詳細位置を計算し、GPSで現地確認した例。
但し、「山島方位記」からの長崎での偏角の解析は、残念ながら測量基点から測量対象地点の山々への距離
が短かいために、解析は困難を伴い解析未了であるが、今後方法の改善を試みたい。
(4) 山島方位記から測量基点の詳細位置を計算し、GPSで現地確認した例。
 <写真3:牛津新町牛印
復元計算位置をGPSで辿ると、佐賀県小城市牛津町
牛津の砥川大橋東詰南側になる。対岸の家の右軒下から
右側が長崎街道で、現在の橋は右へずらして架け替え
られており、牛津新町牛印 は長崎街道の旧砥川大橋の
東詰めと裏付けられた。>
<写真3:牛津新町牛印
復元計算位置をGPSで辿ると、佐賀県小城市牛津町
牛津の砥川大橋東詰南側になる。対岸の家の右軒下から
右側が長崎街道で、現在の橋は右へずらして架け替え
られており、牛津新町牛印 は長崎街道の旧砥川大橋の
東詰めと裏付けられた。>
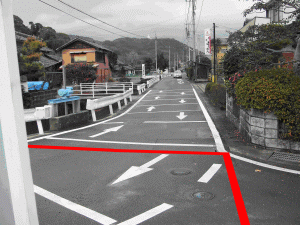 <写真4:牛津下砥川永印
佐賀県小城市牛津町下砥川長崎街道の曲がり角付近を算出。
測量基点は道幅4m四角の中に限られる。>
<写真4:牛津下砥川永印
佐賀県小城市牛津町下砥川長崎街道の曲がり角付近を算出。
測量基点は道幅4m四角の中に限られる。>
 <写真5:伊田浦一印
高知県幡多郡黒潮町伊田浦の伊ノ岬の東側の海岸沿いの
遍路道には、「一里塚」という伝承地名がある。復元
計算による「伊田浦一印」の緯度経度位置は、「一里塚」
の地点の崖下の海岸になる。崖上の遍路道からは、測量
対象の山々は見えないが、写真右の大岩の根元からは測量
対象の山々が見え、伝承地名を裏付けた。今後の更なる
調査の必要性を感じる。>
<写真5:伊田浦一印
高知県幡多郡黒潮町伊田浦の伊ノ岬の東側の海岸沿いの
遍路道には、「一里塚」という伝承地名がある。復元
計算による「伊田浦一印」の緯度経度位置は、「一里塚」
の地点の崖下の海岸になる。崖上の遍路道からは、測量
対象の山々は見えないが、写真右の大岩の根元からは測量
対象の山々が見え、伝承地名を裏付けた。今後の更なる
調査の必要性を感じる。>
<出典>
シーボルト日記 再来日時の幕末見聞記 石山禎一・牧幸一訳八坂書房 P345覚書地磁気偏角の公式 Krusenstern 世界周航図 九州大学図書館デジタルアーカイブス
<助成指定>
本研究は平成二十一年度日本学術振興会科学研究費補助金奨励研究助成を受けました。
(辻本元博 - 日本国際地図学会
面谷明俊 - (有)山陰システムコンサルタント)